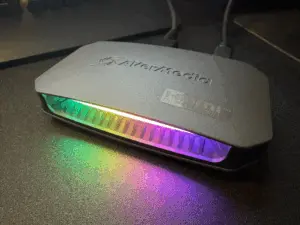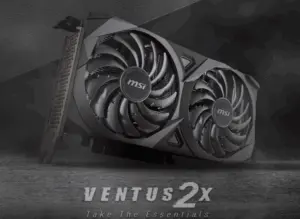【浅草寺】四万六千日・ほおずき市(しまんろくせんにち)、一生分のご利益を
浅草に住む父とメールのやり取りをする中で「今日明日はほおづき市」という内容があり、聞いてみると「しまんろくせんにち(四万六千日)といって今日お参りすれば一生分のご利益があると言われている」との事。
「年換算すると120年ぐらいで人の「一生」に相当するというのと、米一升を数えると4万6千粒になり一升で「一生」をかけているらしい。洒落てるよね〜」
こういう感覚が好きです、浅草も親父も。
一生分のご利益があると言われるなら行くしかありませんね。

人、人、人ですっごい人。そして外国の方々が多いこと。

所々で「ほおずき」が売られておりこちらは「鬼灯(ほおずき)」で「鬼燈(ほおずき)」と表示しているお店もありました。

こちらは「酸漿(ほおずき」。

いたるところにほおずきのお店がありました。

しかし浅草寺のホームページを見てみると

7月9日・10日、浅草寺境内を彩るほおずきの屋台は、浅草の夏の風物詩である。この両日は四万六千日の縁日であり、縁日にともなってほおずき市が催される。
平安時代頃より、観世音菩薩の縁日には毎月18日があてられてきたが、室町時代末期(16世紀半ば)頃から、「功徳日」といわれる縁日が設けられるようになった。功徳日とは、その日に参拝すると、100日、1,000日分などの功徳が得られるという特別な日を指す。功徳日は寺社によって異なるが、現在、浅草寺では月に1度、年に12回の功徳日を設けている。このうち7月10日は最大のもので、46,000日分の功徳があるとされることから、特に「四万六千日」と呼ばれる。この数の由来は諸説あり、米の一升が米粒46,000粒にあたり、一升と一生をかけたともいわれるが、定かではない。46,000日はおよそ126年に相当し、人の寿命の限界ともいえるため、「一生分の功徳が得られる縁日」である。
四万六千日の縁日の参拝は江戸時代には定着し、われ先に参拝しようという気持ちから、前日9日から境内は参拝者で賑わうようになった。このため、9日、10日の両日が縁日とされ、現在に至る。
四万六千日にともなうほおずき市の起源は、明和年間(1764〜72)とされる。四万六千日の縁日は浅草寺にならって他の寺社でも行なわれるようになり、芝の愛宕神社では四万六千日の縁日にほおずきの市が立った。「ほおずきの実を水で鵜呑み(丸飲み)すれば、大人は癪(なかなか治らない持病)を切り、子供は虫気(腹の中にいると考えられた虫による腹痛など)を去る」という民間信仰があり、ほおずきを求める人で賑わったそうである。その愛宕神社のほおずき市の影響を受け、四万六千日の大本である浅草寺にもほおずき市が立った。ちょうどお盆の季節でもあり、ほおずきを盆棚飾りに用いる方も多い。
かつては、四万六千日の縁日に赤とうもろこしを売る屋台もあった。これは赤とうもろこしが落雷除けのお守りになる由の民間信仰により、文化年間(1804〜18)頃に境内で売られるようになったという。ところが明治初年(1868)頃、不作によって赤とうもろこしが出回らないことがあった。これに困ったご信徒が浅草寺に雷除けのお守りを求めた縁から、浅草寺では竹串に挟んだ三角形の守護札を授与するようになった。これが今も四万六千日に授与されている雷除札である。
9日・10日の両日、いなせな恰好の売り子たちが声をあげてほおずきを売り、境内は朝から晩まで参拝者で埋まる。観世音菩薩の功徳に感謝して参拝し、ほおずき市を散策して江戸情緒を味わいたい。
ほおずきはひらがなで表記されているので、好きな方を使えば良さそうですね。
酸漿に関しては見た目的には「サン」から始まるように読めるのですが、実際に生薬の名前としてほおずきを乾燥させたものを"酸漿(さんしょう)"、根を水洗いして日干しにしたものを"酸漿根(さんしょうこん)"と呼ぶそうでどちらも用途としては
咳止め、解熱、利尿薬として発熱、黄疸、水腫に用います。
との事。(創業昭和8年の老舗、馬場薬局ホームページより)
7月8月で咳止め解熱って事は夏カゼに効くお薬だったのかな~と勝手に想像、ナス科でありながら鑑賞用の実にはアルカロイドという毒があるそうで妊婦が服用すると堕胎作用があるそう、花言葉に「浮気」があるヤバめの草だったりします。
生薬として見るなら酸漿。(用途)
行事として見るなら鬼灯または鬼燈。(見た目)
こんな所だろうか、まぁ行事として売っているお店も自由に表現しているし結果自由ですね🤣
ん~しかし昔の人はホント凄い、成分分析もするだろうけど結局は人体実験するしかないだろうに…浮気して毒で堕胎とか怖すぎる😂
・
・・
・・・
どんな結果になろうとも後悔しないようやれることはやる、
神頼みではなく「やれることはやっておく」。