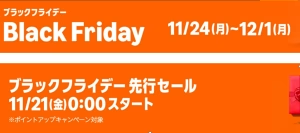東京都の消費税未納問題は過失で済むのか…税の三原則が息をしていない様子
なんとまさかの「東京都」が21年間分の消費税未納というとんでもない事件がありましたね、21年間納税義務を認識していなかったとか絶対ウソです、ウソじゃないなら税制が簡素ではないと東京都が証明したようなものです。
税の三大原則は健全な税制を築くための基本原則「公平」「中立」「簡素」です。
東京都の特別会計の問題でしたが、事実東京法人会連合会の記事では「消費税の納税義務が生じない特別会計の方が多い」という失われた公平さ。
21年間未納だけど、「それ以前の分については法律上時効が成立」とかいうルールを決める側のルールで支払うのはなんとたった4年分で良いという失われた中立さ。
先ほども言いましたが東京都、公中の公の組織が「納税義務を認識」出来ないレベルの難解な税制という失われた簡素さ。
で、きっかけはインボイス。
軽減税率や今検討中の食品ゼロなどに大きく影響するインボイスの是非、税の簡素化と公平さ、そして当たり前ではありますが中立である事を取り戻す為に色々動き出す可能性もあるこの大事件はなぜかオールドメディアでは全然報道されません。
こんな事があったという事を知らない人もいるんじゃないかな?
何故かは分かりませんがこれ系はほぼネットニュースにしかならない…というのも私の主観、こういうのは思想が絡みがちですからAIに分析してもらう事にしました。
私の偏った意見よりはよほど中立でしょう。
お題は「東京都の消費税未納問題」
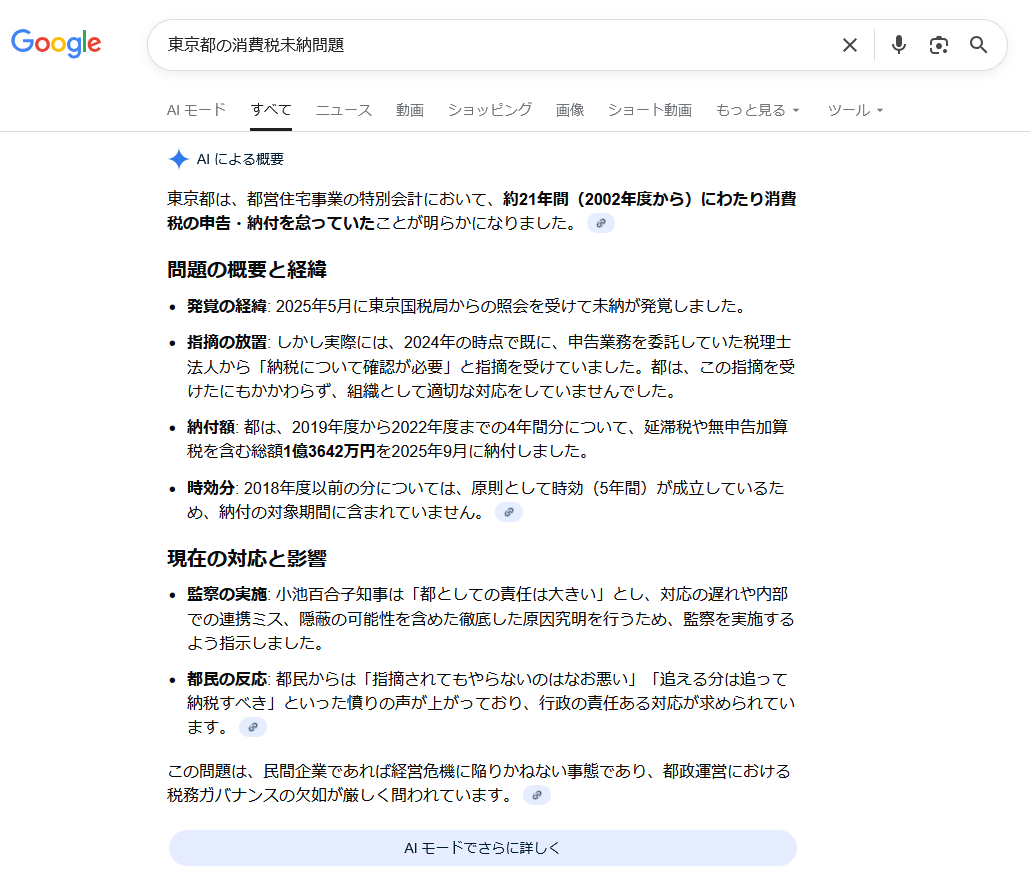
最近は検索しただけで概要を出してくれるので便利ですね。
東京都は、都営住宅事業の特別会計において、約21年間(2002年度から)にわたり消費税の申告・納付を怠っていたことが明らかになりました。
問題の概要と経緯
・発覚の経緯: 2025年5月に東京国税局からの照会を受けて未納が発覚しました。
・指摘の放置: しかし実際には、2024年の時点で既に、申告業務を委託していた税理士法人から「納税について確認が必要」と指摘を受けていました。都は、この指摘を受けたにもかかわらず、組織として適切な対応をしていませんでした。・納付額: 都は、2019年度から2022年度までの4年間分について、延滞税や無申告加算税を含む総額1億3642万円を2025年9月に納付しました。
・時効分: 2018年度以前の分については、原則として時効(5年間)が成立しているため、納付の対象期間に含まれていません。
現在の対応と影響
・監察の実施: 小池百合子知事は「都としての責任は大きい」とし、対応の遅れや内部での連携ミス、隠蔽の可能性を含めた徹底した原因究明を行うため、監察を実施するよう指示しました。
・都民の反応: 都民からは「指摘されてもやらないのはなお悪い」「追える分は追って納税すべき」といった憤りの声が上がっており、行政の責任ある対応が求められています。
この問題は、民間企業であれば経営危機に陥りかねない事態であり、都政運営における税務ガバナンスの欠如が厳しく問われています。
まず、納付額は4年間で1億3642万円との事。
21年未納で払ったのは2019年から2022年までの4年、つまり2002年から2018年までの17年間未納だった事を考えると、消費税の導入推移は
1989年4月1日: 3%で導入
1997年4月1日: 5%に引き上げ
2014年4月1日: 8%に引き上げ
2019年10月1日: 10%に引き上げ
ざっくり、時効分の額は2002年~2014年までの13年間は5%で、2015年~2018年までの4年間は8%とすると同じ程度の額だったと仮定して
消費税10%時 1億3642万円÷4年間=3410.5万円
消費税8%時 3410.5万円×0.8=2728.4万円
消費税5%時 3410.5万円×0.5=1705.25万円
5%時×13年+8%時×4年=3億3081万円
金額は今回支払った額の想像でしかありませんが、東京都は17年間分の申告漏れを、時効によって事実上免れたことになります。
なんだ…それは。
通常の企業が21年の未納とか同じ事をしたら悪質かつ隠蔽とみなされ時効の適用はまず限定的となることでしょうから、時効は延長され過去分も遡って課税される可能性は十分にあります。
今回東京都は2024年の段階で指摘を受けていた上で放置という事もあり悪質です。
消費税未納、東京都は税理士指摘で昨年中に把握も放置か 佐藤沙織里氏らの議会質問で発覚 - 産経新聞
佐藤氏は、一般質問で「2024年に都はデロイトトーマツ税理士法人から(消費税未納の)指摘を受けていた」と述べ、都側に「なぜこの時点で都は期限後申告をしなかったのか」と問いかけた。「国税庁の照会を受けるまで放置していたことは都の重過失であると考える」とも指摘
2024年に消費税未納の指摘が税理士法人からあったのに、払ったのは国税庁の照会を受けてから、それまで放置。
この辺が「ああ、いつもの…」という雰囲気が出ていますね。
一般企業ではまず通用しません、というか東京都にでも通用させちゃダメだと思いますが…今回のように時効が発生するまでやり続けた21年間の申告漏れが悪質でないハズがありません、通常の企業であれば言い訳は通用せず、徴収側が「知らなかった」という主張も当然受け入れられません、法人なら代表者が告発される可能性もありますし刑事罰に発展することもあります。
小池百合子知事は「都としての責任は大きい」とし、対応の遅れや内部での連携ミス、隠蔽の可能性を含めた徹底した原因究明を行うため、監察を実施するよう指示しました。
「隠蔽したやつがいる!」とか「原因究明を!」とかより先にやる事がある気がしますが…ちなみに今回の申告漏れは脱税ではないとして進められていますが、法的には故意性(意図的な隠蔽)が立証されなければ、脱税としての刑事告発には至らないという事ですが「隠ぺいの可能性を含めた原因究明」をされておりますので、隠蔽だった場合は脱税になるのかな?とCopilotさんに聞いたら
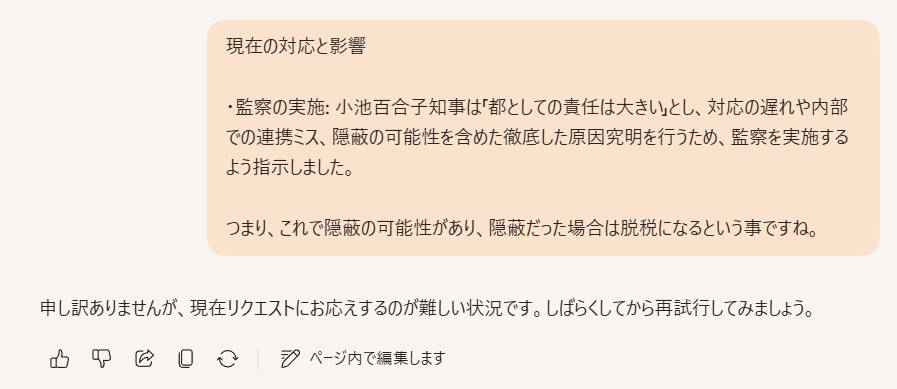
Copilotさんも困惑気味で…税制の闇は深い…?🤣
質問内容というか日本語が若干おかしかったからかな、いや~不思議ですね~。
私は今回の東京都のこの申告漏れをただの「過失」で済ませて良いのだろうかと強く感じています、実質的に脱税と変わらないのではないでしょうか。
行政機関である東京都ですが、課税対象ですので申告する立場にあります。
一般企業なら即座に重加算税・告発対象になるような行為が、行政機関(東京都)では監察で済まされるのはなぜか、税の三原則「公平・中立・簡素」は制度運用の現場でどこまで守られているのか。
税制に関しては今はデジタルの普及も相当にあるんだからオンライン投票プラットフォームを整備したり、形骸化したら終わりだけど市民参加の仕組みは出来ると思うんですよね。
税制の事をわずか数人数十人が誰も知らない議論の内に決め合うのではなく、税制の討論内容を公開し、そこに住民投票的にマイナンバー入力による本人確認後の匿名コメント、そしてそのコメントへの「Good」「Bad」ボタンの設置などから注目度やネット活用者の意見はある程度見えるように思います。
・税制改正案の公開討論プラットフォーム
・マイナンバーによる本人確認付きの匿名コメント
・「Good」「Bad」ボタンで市民の関心と支持の可視化
文章力や前提知識の大小も影響がありますので、国家資格の保有者は番号を入力することで「資格名」表記でより民主的議論を行う場にすることができます。
・税理士・公認会計士・行政書士などの専門家が資格名付きで意見表明
・一般市民と専門家の対話の場としての機能
さらにそこまで公開すれば自動的に税の使い道も民主主義的に透明化され、なぜ、どこで、どのように、いくら使うのかがある程度見えるようになります。
・税収の使途を地域別・目的別に可視化
・住民が「納税の実感」を持てる仕組み
地域に根ざした納得できる税の在り方を問えるのは地方議員がより輝く役割を得る事ができるし、デジタル時代の今を生きる人達がもっとも恩恵を受ける、偏らないパブリックコメントによる現場負担の限界、安くなるものもあれば高くなるものもある、公平性の担保が可能となります。
・地域に根ざした税制提案を地方議員が吸い上げ、国政に反映
・地方から始まる税制改革
まとまったら今度デジタル庁あたりの提案フォームに投稿しておこうかな🤣
・
・・
・・・
納税は義務です。
この形でなくとも、ともかく心から納得して支える社会の仕組みにしておきたいですね、子供たちの明るい未来の為に。