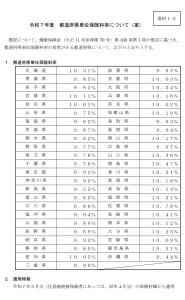ECBは急速利下げターン、コスト増によるインフレを急速に引き締め緩めるとこうなるのか…。
ユーロ圏は供給ショックによるもののようですが物価高、日本同様にコストに押し出される形の中、政策金利を一気に4.5までガンガン引き上げからの急速に引き下げ続け2.75、いやはや強烈ですね。(ECB(欧州中央銀行))

PMIは50を下回ると不況気味、上回ると好景気な様相だという事で2022年からはひたすら下がり続け、2022年の7月からは50を切ってしまいました。
未だ回復する見込みはありません。

S&P GlobalのPMI推移によると製造業はとんでもない状況になっています。
それもそのハズ、2022年6月から超急速に利上げが行われ…

2022年6月~2023年10月というたった1年程度の間に0%から4.5%に上がっています。
これは例えば企業が機械を導入するってんで1億円の融資を10年で受けるとして

ゼロ金利の時は0.50%、4.50%金利の時は5.00%だとすると支払利息合計には700万円程度の差があり、毎月の返済額は10年融資で月6万円の差。

20年ならより極端になり、月14万の違い、全期間の支払い金額では実に3300万円の差が生まれます。
長期になる住宅ローンや耐用年数の長い建物系…つまり新工場や設備拡張などに直接影響がある為、金利上昇は個人だけでなく企業にも大きく影響します。
ECB、0・25%利下げし2・75%へ…4会合連続で政策金利引き下げ
【フランクフルト=秋山洋成】欧州中央銀行(ECB)は30日、定例理事会を開き、民間銀行がECBにお金を預ける際に適用する「中銀預入金利」を0・25%引き下げ、2・75%とすることを決めた。政策金利の引き下げは4会合連続となる。
ECBは声明で「経済は依然として逆風に直面しているが、金融引き締めの影響は徐々に薄れつつあり、時間の経過とともに需要は回復するだろう」とした。
ECBは昨年6月に4年9か月ぶりの利下げを決めて以降、急速に金利引き下げを進めてきた。この結果、2%のインフレ(物価上昇)目標が視野に入りつつある一方、欧州経済の弱含みは続いている。
ドイツ政府は29日、2025年の経済成長率の見通しを、従来の1・1%から0・3%に引き下げた。米国のトランプ大統領がEU(欧州連合)への関税引き上げを検討しており、最大の輸出相手国・米国との貿易で不透明感が強まっていることが一因だ。
3会合続けて利下げしてきた米連邦準備制度理事会(FRB)は、1月会合では金利を据え置いたが、ECBは域内景気下支えのために利下げを選択し、判断が分かれた。
先述した通り需要が爆伸びしているワケではなさそうですし、通貨が弱まるほどの影響は出ていない。
「一度やってみて、問題無いところまで下げる」
で、程よい場所まで利下げを行うのは良い対策のように思います。
が、少し急すぎて金融市場がとんでもない事になりそうです、引き下げの効果も空しく弱含みは続く…という事はまだ足りないという事。
短期で急にドンと行うよりは、利上げするのは過熱抑制として過度のインフレや通貨価値下落を防ぐという分かりやすい経済指標により効果が分かりますし、適正なタイミングで行う利上げは長期的には個人や企業にとってもに良い状態でありますが、利下げするタイミングは本当に難しいと思います。
金利が低ければ住宅ローンも安いけど預金金利も下がる、長期資産を持っているなら返済は緩いので利回りが取れるけど体力が無いから賃料は取れない。
緻密な計画をもって適正かつ長期的に緩やかに政策金利は定めるものだと思います。
今回のように2月には経済の見通しでマイナス成長って発表されちゃうからもう利上げするの難しくなるし駆け込み利上げ!とかならもうほんと言語道断です。
諸々のコストが増加した結果物価が上がっているのに物価抑制したら上がったコストにはどう対応するのか
日本の製造業PMI 2023年1月~2025年1月

日本の製造業PMIはほとんどの期間で50を下回っています、そして去年7月の利上げ、そして今回の同水準の利上げにより冷え込み、その他諸々の要素により予想では50を上回るという事ですが…さて、どうなるか。